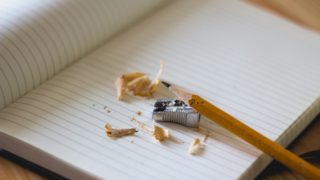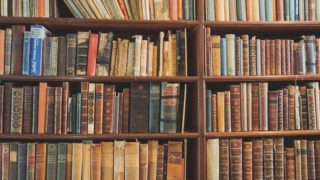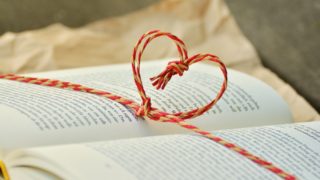授業でわからないところ先生に質問するときに、その質問の仕方が下手だと先生を困らせてしまうことがあります。
例えば、よくあるのが
- 「何がわからないのかわかりません」
- 「ここがわかりません」
などのアバウトな内容の質問では、先生もどう教えればいいのかわからず困ってしまうものです。
漠然とした質問をするよりも前に、まずは自分の質問したい問題は何なのかを整理しておく、質問の内容を事前にまとめておいて、ちゃんと先生に伝わるようにしておくなどの質問の準備しておくことが大事なのです。
今回は、勉強の質問の仕方やコツについてまとめました。
質問下手だと余計に先生を困らせてしまう…
まずはじめに、分からない問題を質問することは恥ずかしいことではありません。
分からないことをしっかり聞いて分かろうとする心構えは勉強に限らず仕事でもスポーツでも大事です。
しかし、先生と言ってもやはり他人である以上は、自分がわからなくても悩んでいることを全てわかってくれるわけではありません。ましてやエスパーやテレパシーを使って言葉ではうまく表現できないことまで全て理解してくれるというわけではありません。
それゆえに、質問をするときは事前に準備をしてから質問に行くことが大事なのです。
お医者さんに自分の体の不調や症状を丁寧に説明するように、自分が今どんな問題がわからなくて困っているのか、どこがわからなくてつまづいているのかは、自分が一番よく知っているものです。
その説明をせずに、ただ漠然と「ここがわかりません」と先生に質問しても、先生からすれば「君は一体何がわからなくて困っているのかわからない」という返事になるのも無理はありません。
先生に質問したけど全く参考にならなかったと嘆いている人は、先生に文句を言うよりも前に、
- ひょっとしたら自分の質問が説明不足だったのでは?
- もっと質問する内容を整理しておいたほうがいい説明が聞けたのでは?
と、自分の質問の仕方を振り返ってみる習慣をつけるようにしましょう。
スポンサーリンク
勉強で先生に質問するとき押さえておきたいコツ
質問する内容を具体的にしておく
ただ教科書を持ってきた「この問題がわかりません」と言われても、先生にからすればどう説明すればいいのかわからずお手上げです。
ですので、質問をするときはなるべく質問する内容を具体的にして、ちゃんと先生に理解してもらいやすいようにしておくことが大事です。
例えば、数学で二次方程式に関する質問をする場合「この問題がわかりません」という言葉ひとつ見ても、
- 「この問題の答えがなぜ○○になるのかがわかりません」
- 「この問題にはどの公式を使えばいいのかがわかりません」
- 「この問題の途中式がなぜ△△になるのかがわかりません」
- 「この問題で登場する判別式の使い方がわかりません」
など、色々原因は考えらえるはず。
自分がこの中でどれについてわからなくて質問したいのかを明らかにしておくことは大事です。
他にも英語の長文問題の場合だったら、今自分がわからないのは単語、イデオム、文法、文脈、問題の選択肢の選び方…など、まず何がわからないのかを調べておいて、そのことを質問することが大事です。
そのほかにも
- 分からない所が教科書のどのあたり載っているかを調べておく。
- (数学なら)途中式や実際に使った図などを用意しておく。
- わからない箇所をメモで箇条書きにまとめておく。
などの質問する前の準備も大切。先生から見れば具体的であればあるほど、教えるためのヒントが多い状態なのでどこでつまづいているかがわかりやすくなります。
担当の先生以外にも質問してみる
先生に質問すると言っても、その先生がたまたま席を外していたり、どうも相性が合わない場合は他の先生に質問してみるのも方法の一つです。
同じ学校の先生でも教え方や経験の差は異なるもの。また、若い新任の先生だと経験が浅くて答えられないということもなく、逆に年齢が近いことから質問に対する教えかたがわかりやすい、という違いもあるものです。
ですので、一人の先生だけに質問してそれでもわからない場合は、同じ科目の他の先生にも質問して見るようにしましょう。
なお、学校によっては、「自分が教えてもらってる先生以外に質問するのは失礼」という理由で質問していはいけないという暗黙のルールがある学校もあるようです。
しかし、失礼だからと言ってわからないまま放置しておくのは困りもの。
最初は緊張してうまく説明できないこともあるかと思いますが、ぐっと堪えて質問してみる、相談してみて、自分の勉強に役立てるようにしていきましょう。
また、もしも学校の先生には質問しにくいと感じている場合は、個別指導塾や家庭教師の先生に質問してみるのでもOKです。
この時も学校の先生同様に、質問の内容を具体的にして、自分からちゃんと説明するようにこころがけましょう。
質問したその場でちゃんと理解する
質問して説明を受けたまではよかったものの、中途半端な理解になってあやふやなまま…というのはよくありません。
質問をした以上は、ちゃんとその場で説明を理解して自分のわからなかった所を克服することが大事です。
質問したことで満足せずに、質問で理解した知識をもとに演習問題を解いてみる、テストなどの実践で活かせるように、しっかり自分の知識として定着させるように復習をするようにしましょう。
ボキャブラリーを増やしておく
「自分の質問したいことが漠然とあるんやけど、そのことをどう言葉にすればいいかわからずモンモンとした」なんて経験はないでしょうか。
自分の言いたいことがあるけどそれが言葉にできないのはボキャブラリー(語彙力)が不足していることが原因です。
ボキャブラリーを増やすには、単語の知識を勉強して地道に増やすのが効果的です。
- 新聞や小説などの文章を読む
- 読んでいるときに出てきた意味がよくわからない単語を辞書を引いて調べる
- その単語を使った例文を調べてみる
などの、方法でボキャブラリーを増やすことができますが、もちろん、現代文や古文・漢文などの教科書に載っている単語を使って自分の気持ちを文章にするトレーニングをするのでもOKです。
質問がうまくなれば長文問題や小論文や面接にも役立つ
上手な質問をするためには
- 自分で文章を組み立てる
- 相手に伝わりやすいように文章を読み直す
- 自分の気持ちを表現するのに適した言葉を選ぶ
- 自分の主張を明らかにしておく
- 必要なら図や資料を加える
などの、丁寧でわかりやすい文章を書いたり、コミュニケーションをとるのに重要な技術を磨くことができます。
この技術は受験勉強なら英語・国語の長文の読解や長文での解答、数学の証明問題のような理論立てて証明をする問題にも役立つ技術です。
そして長文問題は暗記や知識を問う問題と比べて難しい上に配点が大きくなり、受験の結果を大きく左右する設問なので、普段の質問の仕方でこまめに鍛えておくと自分の強みになり、他の受験生に差をつけることができます。
また、小論文や面接でもこの技術は効果的です。テーマに関して自分の意見を述べる、聞かれた質問に対して、その場で自分の考えを述べるのことは、普段の先生への質問を仕方を応用すればいいのです。
ちなみに、受験や勉強以外にも、質問の仕方を身につけておくことは大事です。
- 部活動でコーチ・監督に質問しに行く
- 友達や恋人に自分の悩みを打ち明ける
- 就職先で困っていることを上司に説明しにくい
など、普段のコミュニケーションでもよく使う技術なので、まずは学校を通してしっかり鍛えておくようにしましょう。