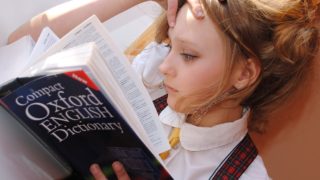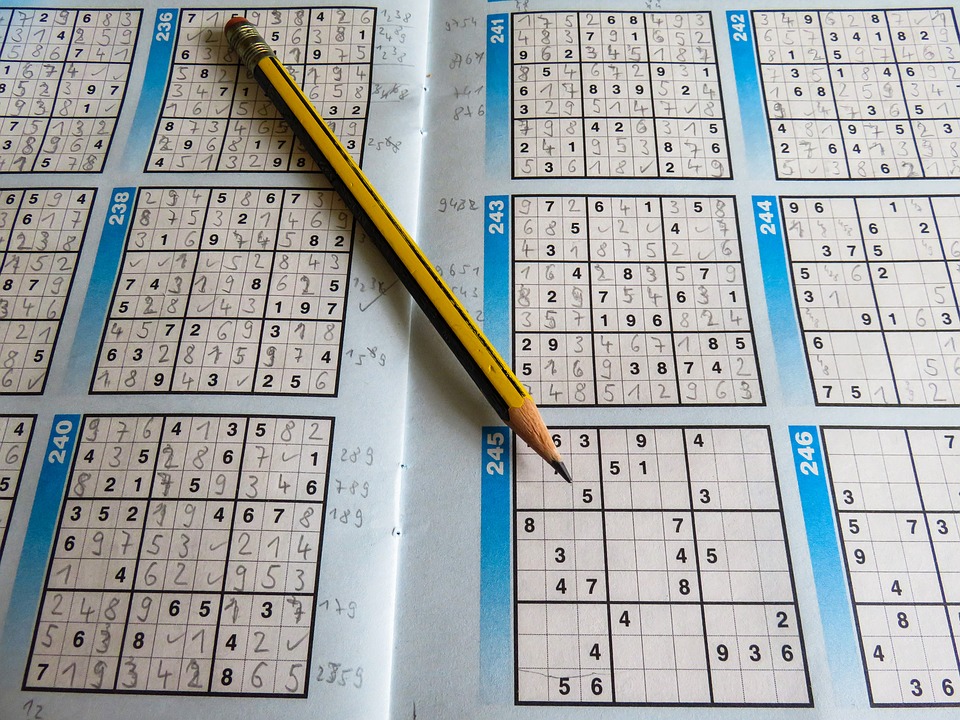テストや模試が返ってきた時に、点数が想像以上に悪かったり、志望校がE判定でショックを受けることは誰でも一度は経験したことがあるかと思います。
しかし、そこでショックを引きずり、その後の勉強のモチベーションを失ってしまったり、どうせ勉強しても無駄だと悟ってしまって、勉強を放棄してしまっては意味がありません。
テストや模試であっても、正しい反省の仕方を身につけて、たとえ悪い結果であっても過度に落ち込まず、結果からしっかり反省すべき点を見つけ出し、次に向けて勉強していくことが、成績アップや志望校合格には大切なことです。
悪い点数をとってしまったという過去は変えられない以上、その過去をどう向き合うかを勉強を通して学んでおくことは、就職活動や仕事の場面でも役に立つ知恵とも言えます。
今回は、テストの成績が悪かった時の反省の仕方に関する知恵についてまとめました。
テストが悪かった時のよくある間違った反省の例
ただクヨクヨと落ち込み時間を無駄にする
テストの点数が悪かったからといってただクヨクヨするばかりで、時間を無駄に消費してしまう反省は効果的ではありません。
クヨクヨしている時間が5分とかならまだしも、30分、1時間となれ場その時間を使ってテストの復習をしたり、解説を元にもう一回問題を解き直してみるといった建設的な勉強をすることができます。
冷静に考えればクヨクヨするだけで成績アップする…というわけではありませんよね。
どうしたら、テストの成績が良くなるか、そのために何を反省すべきなのかで見れば、クヨクヨして時間を浪費するのは決して建設的な反省ではないということがきっとわかると思います。
なお、これは悪い結果をとってしまった本人だけの問題として捉えられがちですが、先生や親といった指導する立場の人が、過度に萎縮させるような声掛けをしていないか、クヨクヨさせるようなキツい言葉を投げかけていないかを振り返ってみることも大事です。
テストの点数が悪かったからといって怒鳴ったり、突き放すような言葉を言うのは、実際になにが原因で悪い結果になったのかを一緒に考えていくのと比較すると手軽にできます。
しかし、その方法が実際に成績アップにつながるかと言うわけではない点を、よく覚えておく必要があります。
たまたま運が悪かっただけと開き直る
クヨクヨするのが良くないからといって「たまたま運が悪かっただけだから、落ち込まなくてもええやん」と開き直ってしまうことも、効果的な反省の仕方とはいえません。
一見するとポジティブになっているので問題ないように思えますが、自分の勉強の結果を運という自分の実力ではコントロールできないものに丸投げしてしている状態です。
無意識のうちに「まともに勉強しても、結果は運次第だから勉強する意味なんてない」という考え方に結びつきやすくなります。
いい成績も悪い成績も運任せ、出たとこ勝負のギャンブル気分…そんな調子で勉強に挑んでは、
- 自分にとって得意な科目は何なのか
- どうすればできなかった問題が解けるようになるのか
- 帰ってきたテストから次回に生かすために学ぶべきことは何なのか
という、着実に自分の点数を取るための知恵を身に付けることが、自然とできなくなってしまいます。
そのほかにも「今日は悪かったけど、次のテストはなんとかなるだろう!」とポジティブなように見えて、具体的に何を反省したのか、反省して次に生かすために何を学んだのかがわからない開き直る反省も正しくはありません。
クヨクヨするのがNGだからと言って、楽観的になりすぎて運任せにするのは自分から勉強を放棄しているのと同じです。
クヨクヨ落ち込んでネガティブ思考に襲われるのと比較すると、ポジティブ思考はざっくり言って「いいもの」という印象が強いですが、見たくない現実や面倒な努力から言い訳をつけて逃げるための口実としてポジティブな言葉が利用されてしまうことにも注意しておくようにしましょう。
先生の教え方やテキストに問題があったと責任転嫁する
結果が悪いのは先生の教え方のせい、テキストの内容が自分にあっていない…など、自分以外の何かに責任転嫁することも、効果的な反省の仕方とはいえません。
もちろん、本当に先生やテキストに問題があるのなら、実際に違う先生に質問をしに言ったり、自分にあった参考書を探して何周か解いてみることで成績アップにつながることもあります。
しかし、責任転嫁をするケースは
- 自分の勉強方法に改善点があることを認めたくない
- 本当はやればできるけど、先生やテキストのせいで実力が発揮できていない
という自分本位な理由になることが大半です。
この考え方では、いくら先生やテキストを取っ替え引っ替えしても、その度に責任転嫁で自分以外の何者かのせいにするくせが身につき、自分の勉強方法や考え方を根本から見直すことができないままになります。
スポンサーリンク
テストの反省は技術的な反省を
テストで反省すべきなのは「どうしたら次のテストに活かせるための知識が身につくか」という視点に立って、冷静に間違った問題を分析したり、わからなかったところの知識を確認して地道に勉強を積み重ねることです。
例えば、英語のテストで長文問題が解けなかったからと言って「自分には英語の才能がないから無理や」と落ち込むのではなく、
- どうして長文問題が解けなかったのか原因を探る(例:単語の知識不足、文法の理解ができていない…など)
- 長文問題を解説を見たり、聞いたり、質問したりして理解しようとする。
- 何度も復習して、解けなかった長文問題を理解して解けるようにする。
という地道な努力を積み重ねて、着実に成績アップするための技術(=知識)を身に付けて行くことが肝心です。
ここでいう「技術」とは、手っ取り早く点を取るための小手先のテクニックのことだけではなく、自分のわからなかった問題がなぜ解けなかったのか理解し、その理解で身につけた知識が次のテストで登場したらしっかり解答できる、という状態になるための技術のことを指します。
上で説明したクヨクヨする、楽観的になる、責任転嫁するという反省の仕方では、成績アップのための技術を付ける反省としては相応しくないことが、これできっとわかると思います。
テストで難問が出て解けなかったり、難問に時間を取られすぎて焦りから普段なら解ける問題でミスして失点することは勉強に取り組んでいる人なら誰でもあることです。
解けない問題のせいで悪い結果になってしまったことを後悔するよりも、どうしたらその難問を理解できるようになるか、その難問を解くのに必要な基礎知識や公式は何だったのか、という次回以降のテストに結びつく技術的な反省をするように心がけましょう。
スポンサーリンク
テストの数字に一喜一憂せず、地道に知識を身につけるべし
テストの結果がよかったら喜んで、悪かったらがっかりする…これ自体はいたって自然な人間の心理です。
しかし、テストの結果に一喜一憂することは、その度に気分の激しい浮き沈みに振り回されてしまい、勉強のモチベーションを乱す原因になってしまうことがあります。
もちろん、「いい点数をとったからといって決して喜ぶんではいけない」というわけではありませんし、自分の実力を噛み締めることはモチベーションを維持するうえでは大切です。
ですが、一喜一憂するだけして
- 自分の不得意科目・分野は何なのかを調べようとしない。
- 技術的な反省が疎かになり、ただテストがやりっぱなしになる。
という状態になる恐れがあるので、一喜一憂せずにしっかりテストや模試を復習して、着実に知識を身につけて行くことが大事なのです。